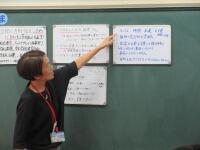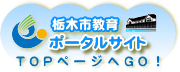文字
背景
行間
カテゴリ:今日の出来事
スポフェスの業間練習の様子です。
【低学年:ダンスの入退場・隊形確認】





【中学年:ダンスの練習】






【高学年:6年生=合小ソーランの声出し練習、5年生=徒競走練習】











【休み時間:代表リレーの高学年児童の練習&開閉会式練習&応援団練習】








「全力で心を燃やして 最後までがんばろう」のスローガン
のもと、来週の本番
に向けて、気持ち
と体力
を高めていきましょう
。
職員研修を行いました。




続いて、特活コミュニケーションです。この会は、自由参加
となりますが、主体的に
研修に参加して
「学業指導の充実
」について話し合いました
。
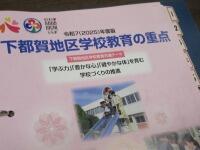



担当の先生から、自身の取組
について説明
がありました
。それをもとに
、グループで
話し合いました
。
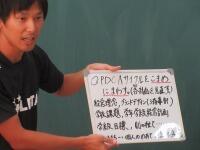



全体で共有しました
。




最後に振り返りの時間です。短時間でしたが、有意義な研修
となりました
。これからも、よりよい授業づくり
について、対話
を通して研修を重ねていきたい
と思います
。
スポフェスの業間練習の様子です。
【低学年:徒競走の練習】









【中学年:まほうのじゅうたんの練習】






【高学年:合小ソーランの練習】








【休み時間:代表リレーの高学年児童の練習】




「全力で心を燃やして 最後までがんばろう」のスローガン
のもと、来週の本番
に向けて、気持ち
と体力
を高めていきましょう
。
スポフェスの業間練習の様子です。
10月6日(月)
今日の業間に、10/16(木)に予定しているスポフェスの練習を行いました
。今回は、低
中
高
のブロック別
に体育館と校庭に分かれて練習
をしました
。
【低学年:玉入れの練習】






【中学年:ダンスの練習】








【高学年:徒競走・障害走の並びの確認と練習】






【休み時間:代表リレーの高学年児童の練習】


「全力で心を燃やして 最後までがんばろう」のスローガン
のもと、来週の本番
に向けて、気持ち
と体力
を高めていきましょう
。
スポフェスの開閉会式の練習をしました。
10月3日(金)
今日の業間に、スポフェスの開閉会式の練習
を行いました。体育主任の先生
から、心構え
の話を聞いて、みんな真剣に取り組みました
。


進行を担当する児童のアナウンス
で、流れを確認しました
。








児童のみなさん、スポフェスの心構え
を意識して
、立派な態度
で練習に参加しましたね
。10/16の本番に向けて
、さらに意識
を高めていきましょう
。
全校除草の様子です。
10月2日(木)
今日の業間清掃の時間は、全校生
で校庭の「除草
」と「石拾い
」を行いました。5年生は宿泊学習に参加しているため、後日に実施します
。まず、環境委員長
より、説明
がありました。「スポフェス前に、自分たちの校庭を自分たちの手できれいにしましょう
」と呼びかけました
。


早速、分担場所に分かれて作業開始です
。1・2年生は石拾い
、3・4・6年生は除草
を行いました。
6年生は、草の多い校庭北側を担当し、一生懸命除草しました。




1・2年生もトラックの石をたくさん拾いました。




3・4年生も除草をがんばりました。




短い時間でしたが、みんな
でがんばってきれいになりました
。環境副委員長
から、終わりの話
がありました。


児童のみなさん、自分たちの校庭を愛校心
をもってきれいにしましたね。この気持ち
を大切に、スポフェス
に向けて、心を一つに
がんばりましょう
。
表彰を行いました。
今回の表彰は3つです
。1つ目
は「新体力テストS認定
」です。2つ目
は「栃木市民水泳大会
」です。3つ目
は「そろばん
」です。
【新体力テストS認定の表彰】



【栃木市民水泳大会表彰】 【そろばん表彰】


表彰された児童のみなさん、おめでとうございます
。これからも、自分自身
を高めていきましょう
。
1・2年生 ダンス練習の様子です。
9月30日(火)
今日の2校時に、1・2年生の合同体育
がありました。スポフェス
のダンス練習
です。それぞれの学年で
練習していて
、今回初めて
、合同での練習
です。動きにも
慣れてきて
、みんな上手に踊っています
。




先生の動きをまねしながら
、練習を進めていきます
。




動きのポイントが分かったら、通して
練習していきます
。






1・2年生のみなさん、楽しんで
練習していましたね
。この調子で
、本番まで元気いっぱいのダンス
が披露できるようがんばりましょう
。
3・4年生 ダンス練習がんばっています。
9月29日(月)
今日の5校時に、3・4年生の合同体育
がありました。スポフェス
で演技するダンスの練習です
。


まずは、音楽に合わせて準備運動です
。楽しみながら
体を動かします
。


続いてダンス練習です。何回か練習を重ねてきて
、土日も家で
練習している子
もたくさんいました
。








音楽に合わせて、体いっぱい使って
表現しています
。


3・4年生のみなさん、楽しく
ダンス練習
に取り組んでいますね
。練習を重ねて
、当日も元気な演技
を披露しましょう
。
教育支援ボランティア よろしくお願いします。
9月26日(金)
今日から、教育支援ボランティアとして、本校
卒業生の大学2年生
が来校し、児童支援
に入ります。朝は、全校生
に向けてあいさつ
しました。その後、主に担当する5年2組
で自己紹介
しました。子どもたち
からも、いろいろな質問
がありました
。




大学の授業との関連で、金曜日に来校予定
です。慣れてきたら
、いろいろな学年の支援を経験
します。将来、学校の先生
を目指しています。先輩のがんばり
を見て、児童のみなさん
も、目標
をもって取り組んでいきましょう
。どうぞ、よろしくお願いします
。
栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上に掲載されている文書や画像等のコンテンツの無断使用・転載・引用を禁じます。
栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。
一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。